制作事例
落合陽一サマースクール
「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」2024年(博多・糸島編)
「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」
クライアント: Table Unstable 実行委員会
2024年制作
2024年7月25日~7月27日 に博多・糸島で開催された、Table Unstable - 落合陽一 サマースクール「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」2024年(博多・糸島編)のダイジェスト映像を制作しました。
1日目は座学、2日目は糸島を巡るアクティビティと制作、3日目は制作した作品の発表会がそれぞれ行われました。制作した作品はNFT化し、地理空間NFTとして現地に配置。さらに映像作品専用ビデオキャンバス Infinite Objects へ格納しました。
3日間の全工程に同行し撮影を行いました。座学でのレクチャー音声などを交えながら、膨大なカリキュラムとなった濃密な3日間を追う映像となりました。また、スマートコントラクトの技術検証についても盛り込んでいます。BGMは、今回のワークショップでの作例として講師の落合陽一氏が Suno で作成したものを使用。
また、弊社山本がティーチングアシスタントとして参加者の子どもたちのグループの1つへつき、制作のレクチャーを行いました。





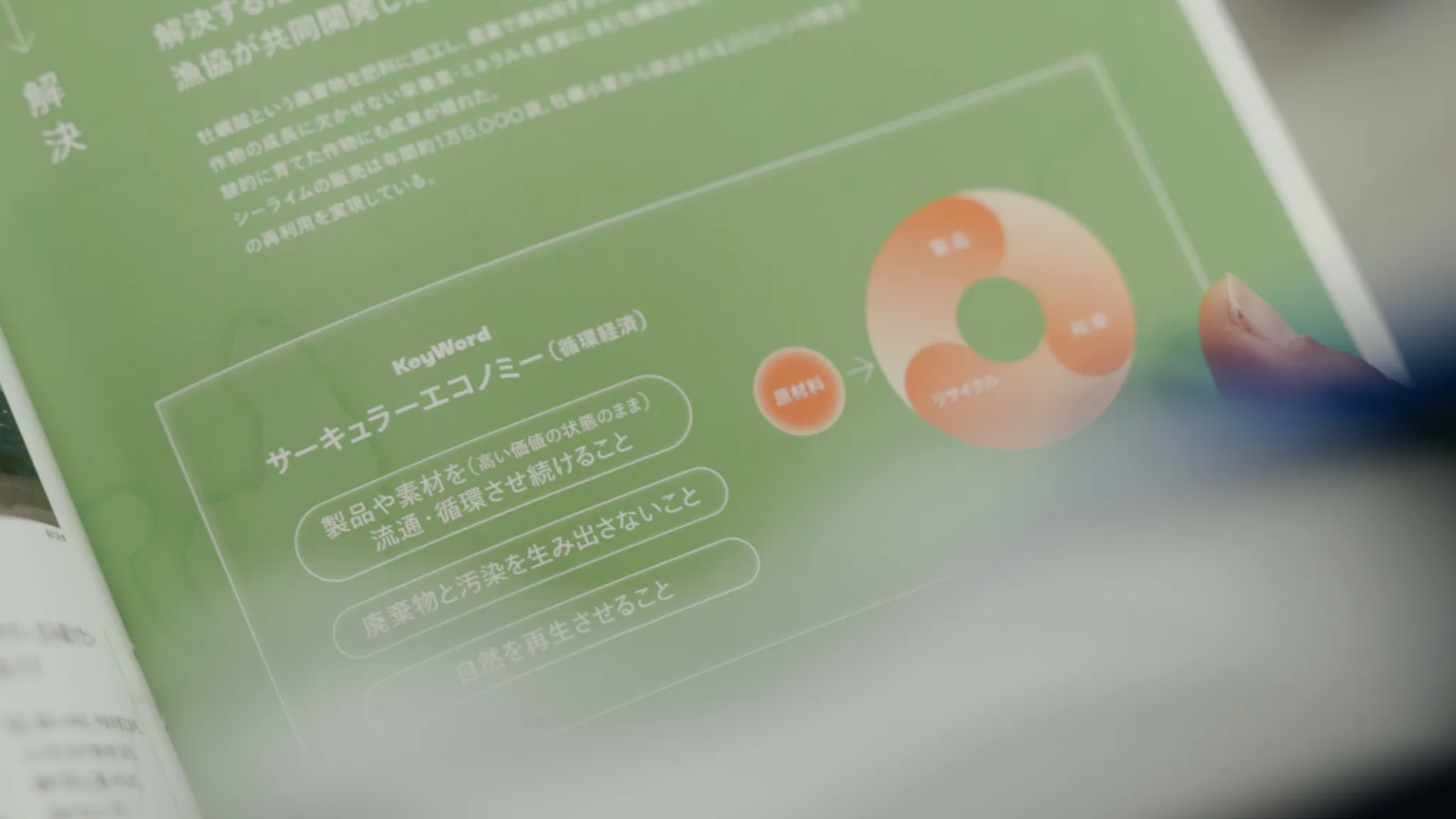

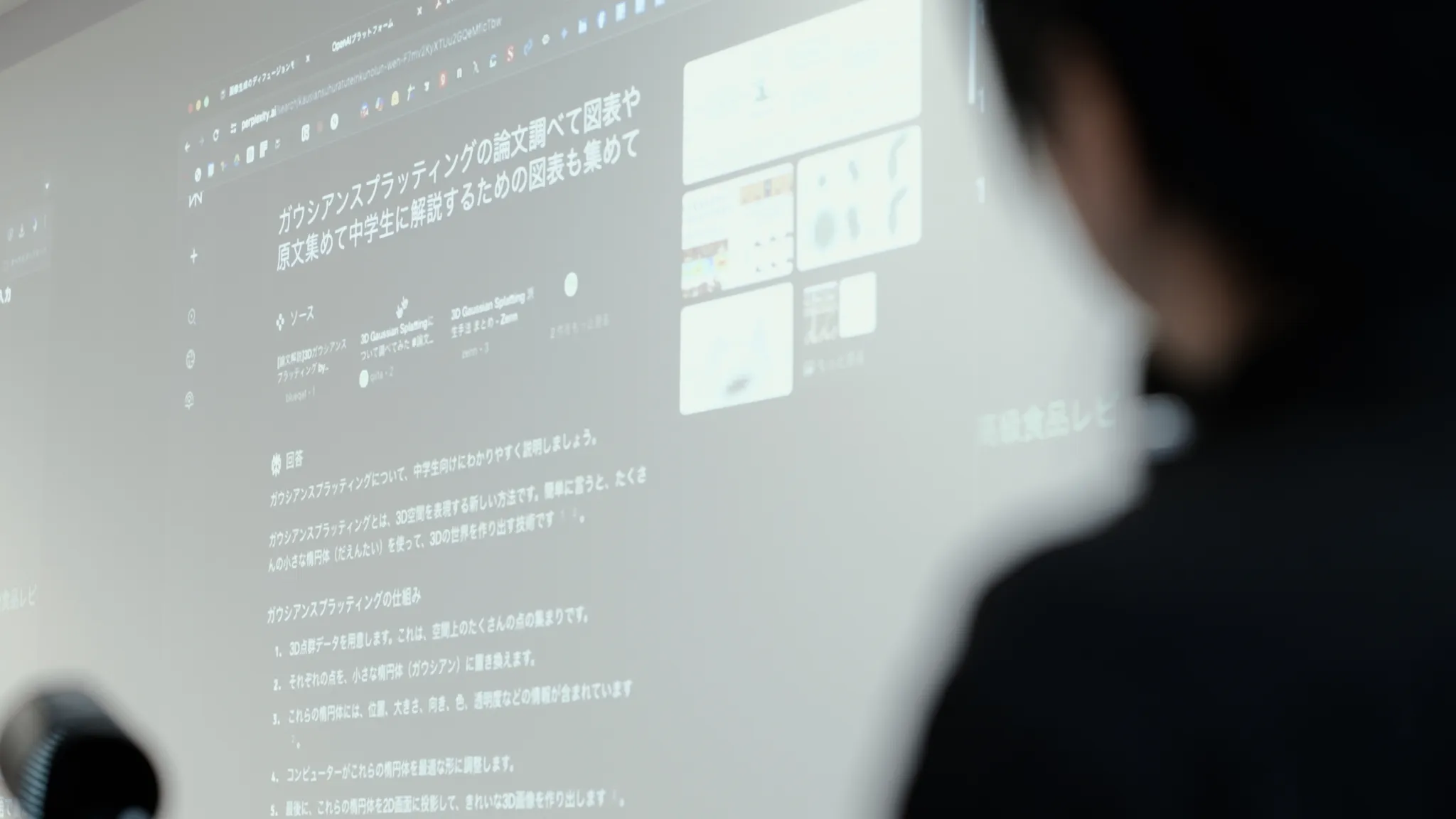




































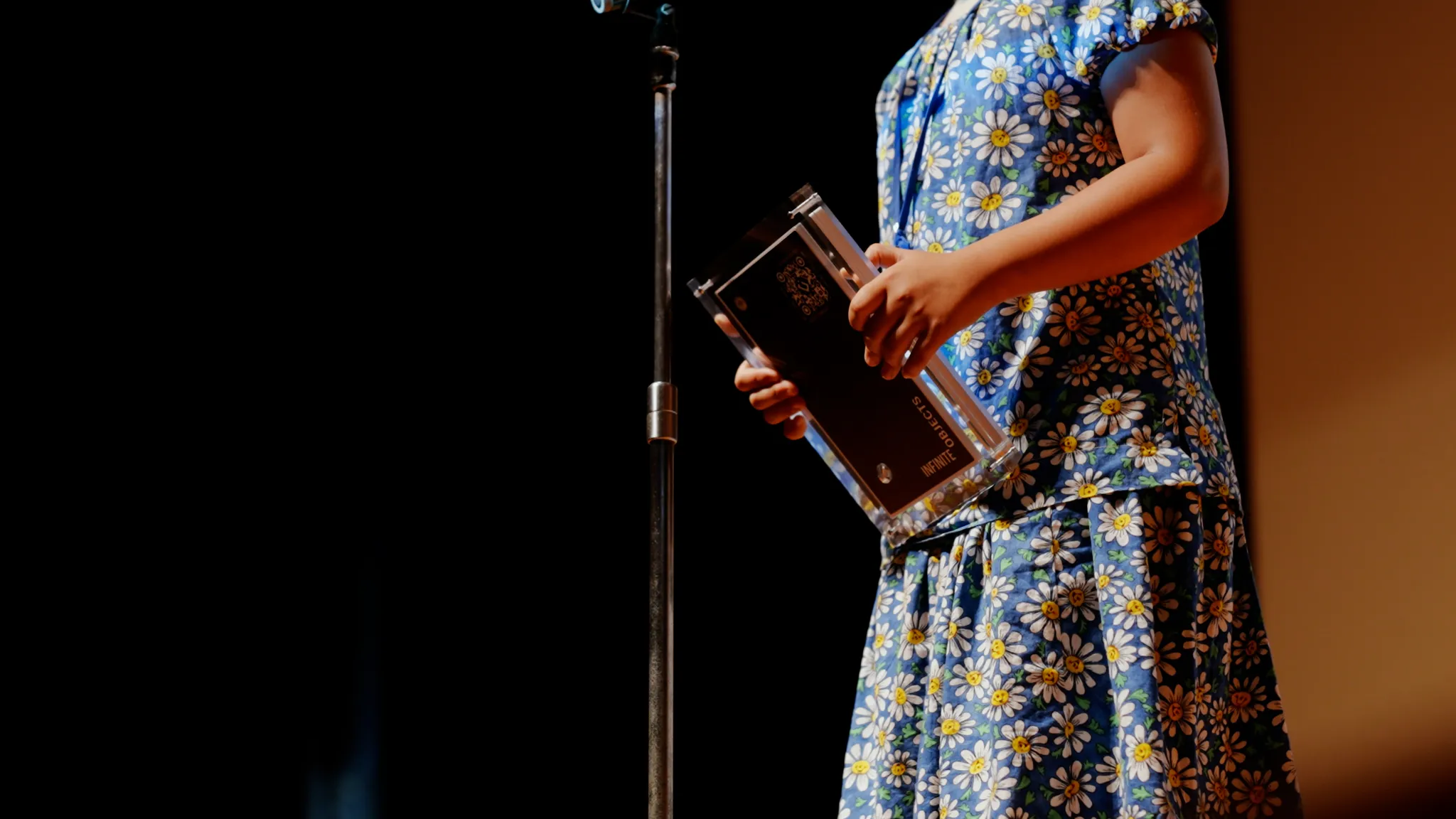







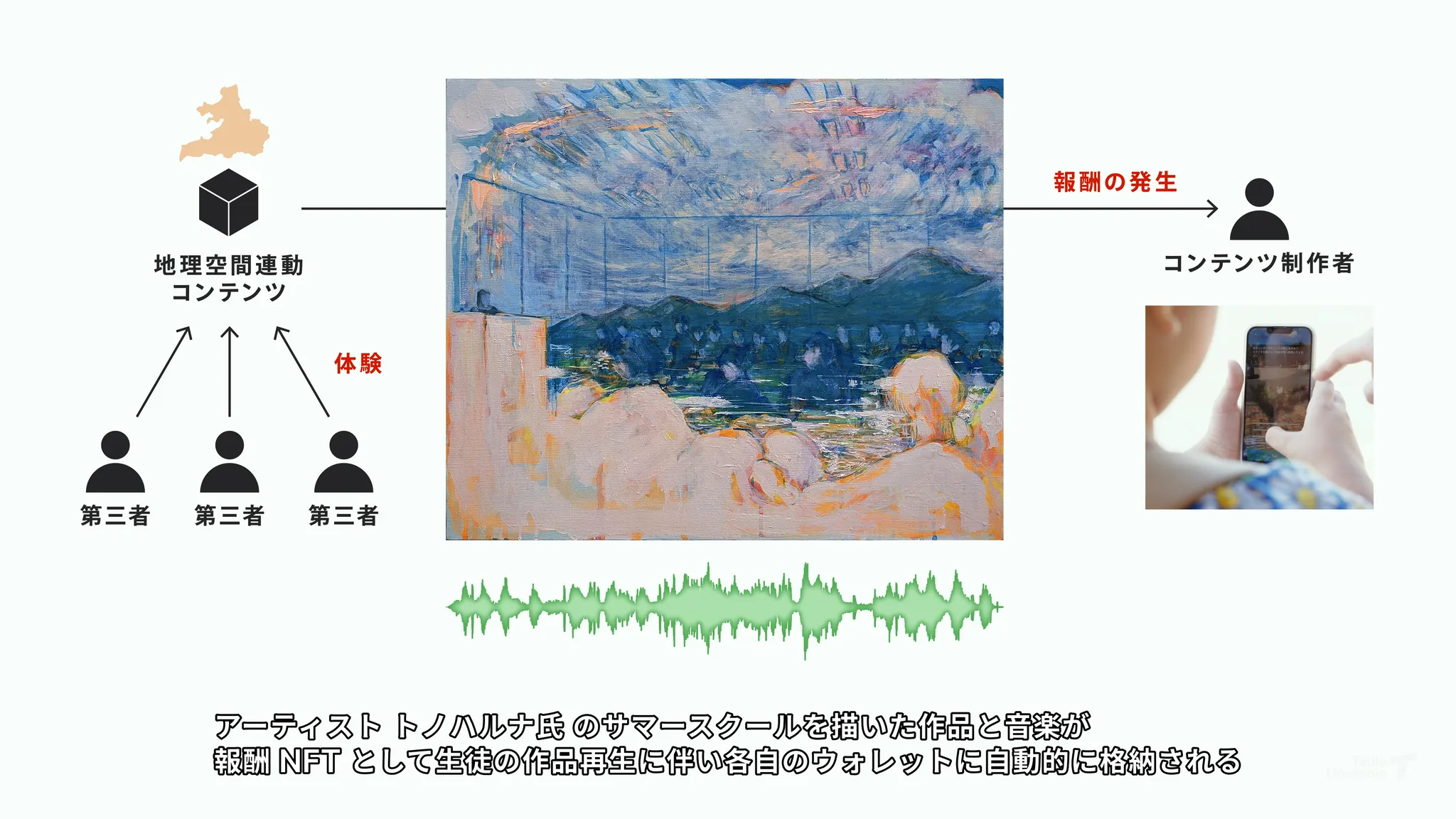



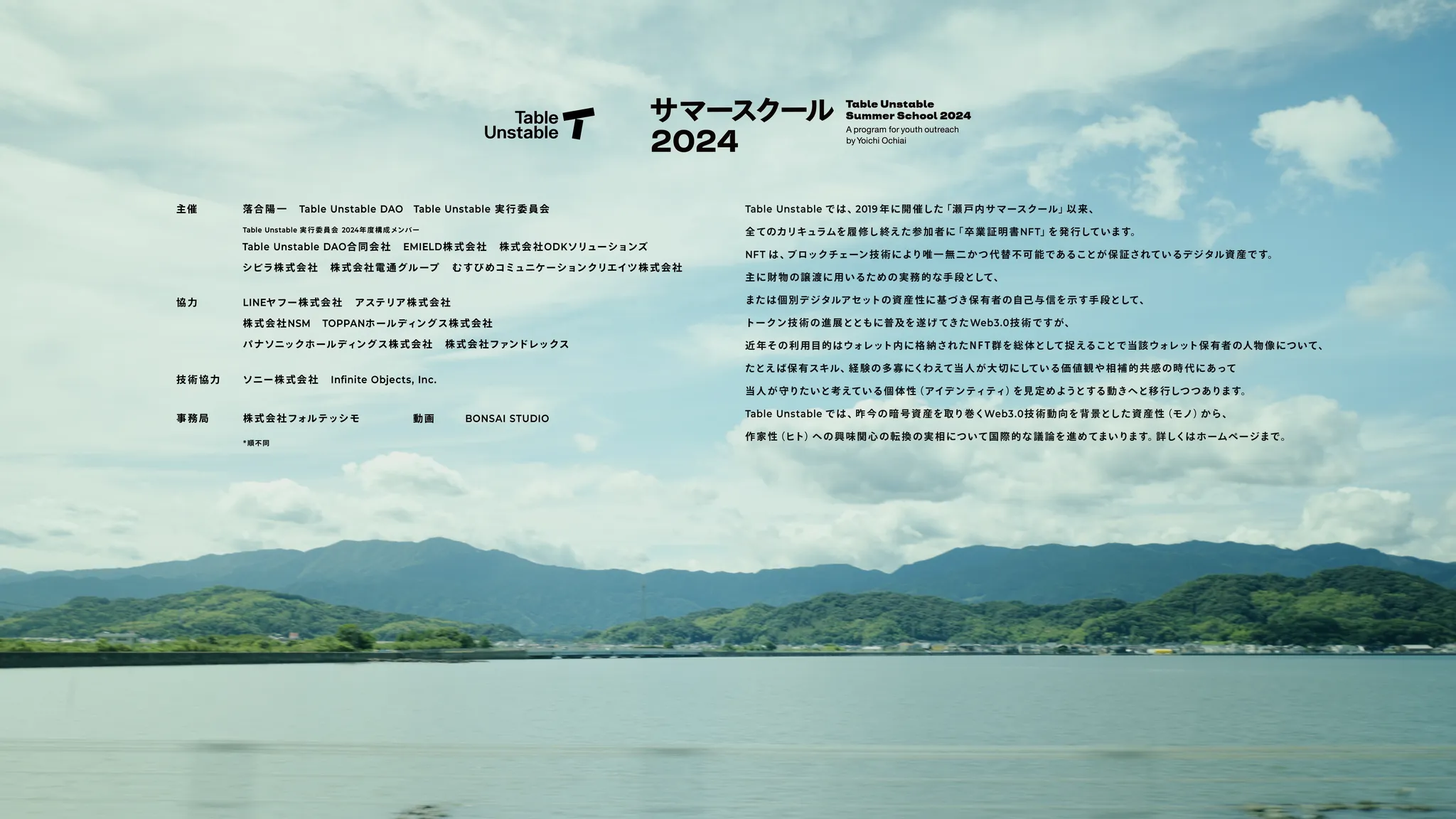
スタッフリスト
監督・撮影・録音・編集
鈴木 一平
BONSAI STUDIO
ティーチングアシスタント・撮影スタッフ
山本 健太
BONSAI STUDIO

